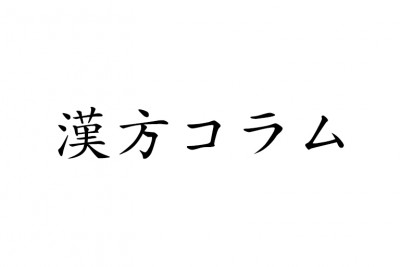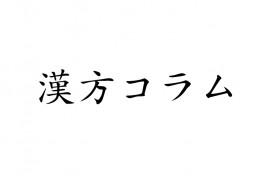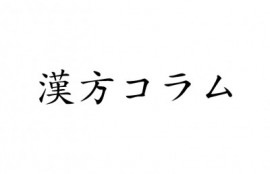疲労とうつ病
今年の6月に東京慈恵会医科大学の研究チームがうつ病の引き金となるウイルス由来のタンパク質を発見したとの報道がありました。同大学の近藤一宏教授によると、まず、疲労が蓄積することでほぼ100%の人に潜伏感染しているとされるヒトヘルペスウイルスの一種であるHHV-6というウイルスが唾液中に急増し、その一部が唾液から鼻に流入して嗅覚と関係する脳の嗅球に感染することでSITH-1というタンパク質がつくられるそうです。次に、このSITH-1の作用で嗅球の細胞にカルシウムを流入させてアポトーシスを引き起こすことで記憶に関係する脳の海馬での神経再生が抑制されるなど脳内でのストレス因子が軒並み上昇するなどしてうつ状態になるというものです。また、実際にうつ病患者の8割近くでSITH-1タンパク質に対する抗体が確認されたとのことです。
疲労倦怠感やうつ病と脳内の炎症に関しては、6年前に理化学研究所からウイルス感染によって脳内で炎症性物質の一つであるインターロイキン1βが産生されて神経炎症が発生していることが疲労倦怠感の原因であるとの発表がありました。更に2年前には京都大学と神戸大学の共同研究で、動物実験で反復ストレスによって自然免疫の受容体であるTLR-2とTLR-4を介して内側前頭前皮質のミクログリアが活性化され、炎症性サイトカインであるインターロイキン1αとTNFαの発現を通じて、内側前頭前皮質の神経細胞の応答性減弱や萎縮、更にうつ様行動を誘導することが確かめられています。
漢方的には“気虚発熱”
現代はストレス社会といわれて久しい上に、新型コロナウイルスによるパンデミックの影響で世界的にストレスが充満しています。実際にロックダウンが行われたアメリカの都市では住民の3分の2が何らかのうつ症状を呈したとする報告もあります。また日本でも新型コロナウイルスに感染していなくても微熱や倦怠感、あるいはうつ的な症状をうったえる人が増えています。
慢性的なストレス状態から微熱と倦怠感が続くケースでは、金元四大家の一人である李東垣が提唱した“脾胃”の虚弱性から陰火が発生する状態、すなわち彼の考案した補中益気湯の目標である気虚発熱とよばれる状態に近いと思います。金元時代というのは中国(宋王朝)が異民族から攻められていた時代で、城壁に囲まれた中国の都市では食料も不足しがちな中で精神的なストレスが充満し、微熱を伴う疲労倦怠感やうつ的な症状を呈する人が増えたと考えられています。そうした時代背景の中で李東垣は“脾胃(胃腸)”機能の低下から陰火が発生していると考えたわけですが、今回の東京慈恵会医科大学の研究でも、“脾胃”の機能低下による気虚(疲労及び免疫力の低下)が引き金となって、脳内で炎症が発生してうつ症状につながることが確かめられたわけで、漢方の世界でも長らく論争をよんでいる気虚発熱の病態の一端を説明できると思います。
気を充実させるには
以上みてきたように、うつ病やそれにつながる慢性疲労を予防するためには気のパワーを充実させることが重要となってきますが、そのためにはまずは“脾胃”の機能を充実させる必要があります。現代医学でも腸内細菌バランスの善し悪しが免疫力に直結することや腸内細菌がセロトニンなどの神経伝達物質をつくりだしていることで脳のストレス抵抗力を高めていることなどもわかっています。一方で、ストレス状態にある方は睡眠障害がみられることが多く、睡眠不足は免疫力の低下に直結します(現代医学でもうつ病の診断基準で睡眠障害は必発条件とされています)。よって、慢性的な疲労感やうつ傾向にある方では、睡眠状態の改善を最優先にして、次に胃腸機能の充実を図るのが根本的な治療につながります。
また、対症療法的には、強い不安感や動悸がみられるときには麝香製剤で滞った“気”の巡りを改善することができますし(麝香には睡眠リズムを整える作用や、おなかを温めて胃腸の“気”の巡りを良くする作用もあります)、疲労感が強くでている場合には蟾酥製剤が、熱感が強い場合には牛黄製剤が有効です。