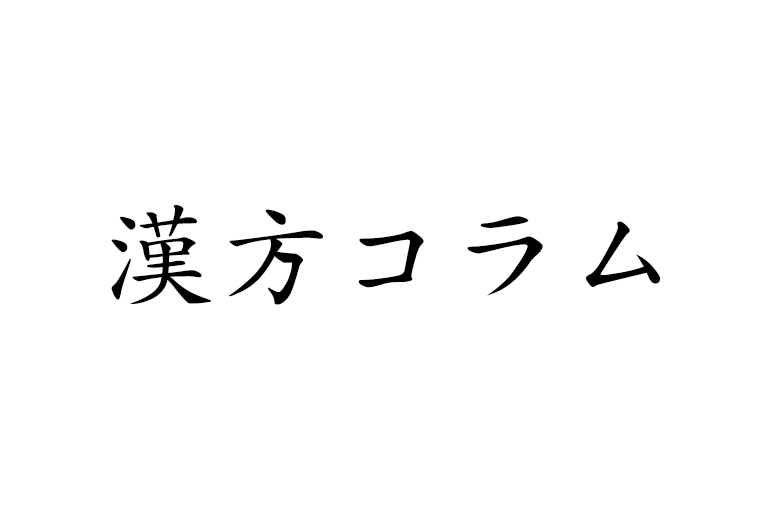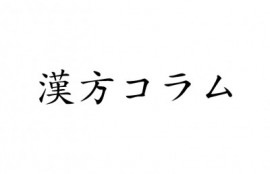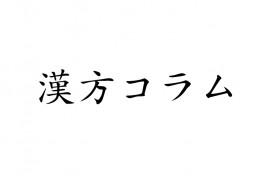仏教における牛玉(ごおう)
四月八日はお釈迦様がお生まれになった日であり、仏教では重要な日とされています。この日は寺院で花御堂と呼ばれる花で飾られた小さなお堂をしつらえ、その中に金属製の幼仏像をおまつりして参拝者が甘茶をそそぐ風習があり、正式には灌仏会(かんぶつえ)といいますが、一般的には“花祭り”と呼ばれています。
さて甘茶に限らず、仏教とつながりの深い生薬は数多くありますが、中でも特筆すべきは何といっても牛黄だと思います。牛黄は四世紀頃に成立したとされる仏教の経典の一つである金光明経にも「瞿盧折娜(くろせつな)」の名で記されており、千二百年以上も続く“お水取り”で知られる奈良、東大寺二月堂の修二会(しゅにえ)や法隆寺で正月に行われる金堂修正会、東京の浅草寺で正月五日に行われる牛玉加持会(ごおうかじえ)など重要な仏教行事に欠かせないものとされています。また、これらの法会では、牛黄を混ぜた墨で文字が記された上に朱印が押された牛玉(ごおう)札が配られ、厄除けの効があるとされています(牛黄を“牛玉”と書くのは、一説に牛玉=ゴーダマが、お釈迦様の名前~ゴーダマ・シッダールタに因んだものであるとか、“ゴーダマ”自体に“最上の牛”という意味があることも関係していると言われています)。
ところで、牛玉札は普通の和紙ではなく、泥紙とも呼ばれる泥土を混ぜ込んだ和紙が用いられています。泥紙は泥を混ぜ込むことで燃えにくくなるために、古来、襖紙としても用いられてきましたが、もう一つの特徴が水に溶けやすいことです。大事なお札ゆえ、燃えにくい紙が使われたともいえますが、牛玉札は水に溶かして服用することまで考えられていたのではないかとも考えられます。実際に東京の水天宮の安産祈願のお札をはじめ、“飲むお札”は全国各地で見られるもので、玄関や壁に貼っておくだけでなく、必要なときに牛玉札を水に溶いて服用していたとしても不思議ではありません。
牛玉(ごおう)の真の“薬効”とは?
では、牛玉札を服用したとしてどのような薬効が期待できたかというと、神農本草経に牛黄の薬効として記されている「なにものかに驚いて卒倒する驚癇の病や寒熱病、発熱が盛んなとき、狂ったようになったり、痙攣の病を治す。邪気を除き、鬼気を逐いはらう」効果だと思います。現代中医学でいうところの開竅作用(精神や意識の混迷を治療する作用)に相当しますが、牛玉札には牛黄の入った墨の文字のほかに朱印(牛玉寶印)が押されており、朱肉は鎮心安神作用のある朱砂であり、牛黄の薬効を補佐することが期待されます。
神農本草経に記された牛黄の効能は普通に解釈すれば精神的なストレスや熱病で精神状態や意識がおかしくなったものを回復させる効果であり、現代薬理的にいうとストレスや発熱によって発生した脳内の活性酸素を消し去る効果です。ただし、仏教の世界に於いて牛黄が最高の霊薬とされていることを考えると、牛玉札というか牛黄は座禅や瞑想を通じて悟りを開く過程で生じやすいからだの不調~禅宗でいうところの禅病と称される状態に用いられたのではないかと想像します。禅病の症状としては座禅や瞑想の最中に突然気分が悪くなったり卒倒したりするほか、慢性化すると頭がのぼせ、手足が冷え、悪夢で眠られないといった状態が続いたりするとされ、正に牛黄の適応となる症状です。
もちろん、牛黄を飲みさえすれば誰でも悟りを開くことが出来るわけではないですが、悟りを開く修行過程に於いて牛黄が重要な役割を担ってきたことは想像に難くなく、牛黄は正に究極の“気つけ薬”といえますし、それゆえに仏教の世界でかくも重要視されてきたように思います。