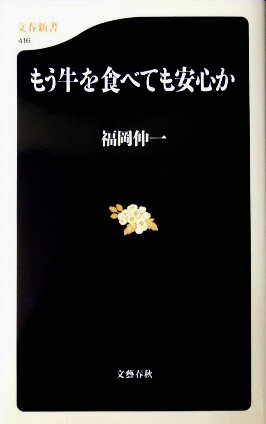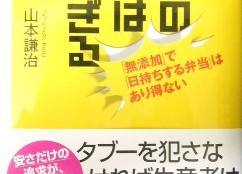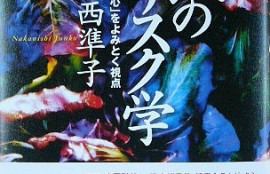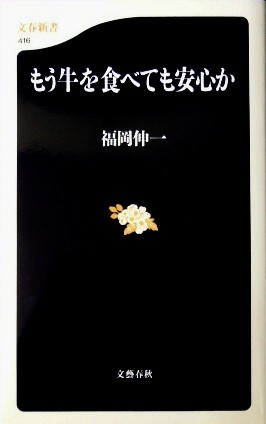 イギリスに於ける狂牛病の発生から、異常なタンパク質〜プリオンが原因という「仮説」が発表されるまでのプロセスが順を追って解説されていますが、この本の主題は狂牛病そのものではなく、1930年代にシェーンハイマーが「発見」した身体の「動的平衡」という概念の紹介から、地球環境全体も我々の身体も動的平衡係の中で、絶えず相互に影響を与えながら、高速で生まれ変わり続けているという認識を持たない限り、狂牛病のような問題は解決されないであろうというのが著者のメッセージとなっています。
イギリスに於ける狂牛病の発生から、異常なタンパク質〜プリオンが原因という「仮説」が発表されるまでのプロセスが順を追って解説されていますが、この本の主題は狂牛病そのものではなく、1930年代にシェーンハイマーが「発見」した身体の「動的平衡」という概念の紹介から、地球環境全体も我々の身体も動的平衡係の中で、絶えず相互に影響を与えながら、高速で生まれ変わり続けているという認識を持たない限り、狂牛病のような問題は解決されないであろうというのが著者のメッセージとなっています。
シェーンハイマーが生物学史上、コペルニクス的な転換をもたらしたとされる実験は、重窒素(15N)を用いてロイシンというアミノ酸を合成し、ネズミに3日間食べさせた後、その間の全排泄物を調べ、更にネズミの体内に、重窒素を含むロイシンがどのように取り込まれたのかを調べるというものでした。
現代人の感覚でも、食べ物に含まれる栄養素をもとにエネルギーを産生し、カスは排泄されるという概念を持っていますが、シェーンハイマーの実験結果は、そういった概念を大きく覆すものでした。エサとして与えた中に含まれていた重窒素の6割近くが、体を構成するタンパク質の中に取り込まれており、更にそのタンパク質はエサとして与えたロイシンというアミノ酸だけではなく、他のアミノ酸に含まれる窒素も重窒素に置き換わっていたというものでした。
この事は、即ち、我々の体を構成している分子が驚くべき速さで入れ替わっていると言うことを示唆しており、この実験結果を受けてシェーンハイマーは「生物が生きているかぎり、栄養学的要求とは無関係に、生体高分子も低分子代謝物質もともに変化して止まない。生命とは代謝機械の持続的変化であり、この変化こそが生命の真の姿である」として、生命の「動的平衡」という概念を世に広めた事が紹介されています。
現在では、体を構成するタンパク質や脂質だけでなく、人間の60兆個あるとされている細胞は、60日間で総て入れ替わることが知られていますが、分子レベルで考えれば、食べ物を構成している分子が、身体を構成している分子と入れ変わり続けているということになり、著者の言葉を借りれば「肉体というものについて、感覚としては、外界と隔てられた個物としての実体があるように私たちは感じているが、分子のレベルでは、たまたまそこに密度が高まっている、分子のゆるい「淀み」でしかない。しかもそれは、高速で入れ換わっている。この回転自体が「生きている」ということである」としています。
著者は、このシェーンハイマーの考え方は、チベット医学の考え方〜人間と宇宙は絶えず手をたずさえて踊っている〜に通じるところがあるとも書いていますが、チベット医学を持ち出すまでもなく、これは漢方の認識そのものでもあります。漢方では「天人合一」説や「整体観」と呼ばれていますが、人間は自然界の中の一部であるというのが漢方の発想の根底にあります。
「食」は養生の基本でもありますが、正に「人は食べた物でできている」訳で、この食べ物は何カロリーですとか、ビタミンCが含まれていますといった事が総てではないという事をもっと認識すべきだと思います。
最後に、狂牛病に関しても、これは人間が手を加えすぎて発生した歪みに対して地球が「平衡」を取り戻そうとしているひとつの表れではないかと、著者は指摘しています。
(文春新書(416)、平成16年12月20日初版、著者の福岡伸一氏は青山学院大学理工学部化学・生命科学科教授)