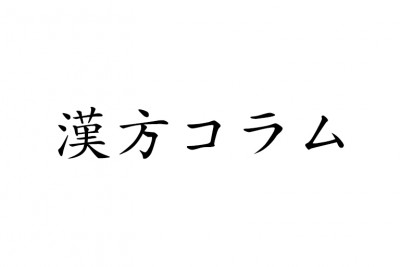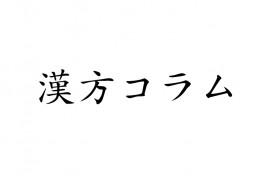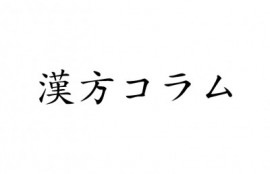がんの過剰診断問題
今年の1月にオーストラリアのボンド大学の研究チームがオーストラリアで1982年と2012年を比較して、2012年にがんと診断される症例が相当数増えているにもかかわらず、この間のがん死亡数が増えていないことなどから、がんの過剰診断が増えているとする論文を発表しました。同研究チームによると、2012年では、男性のがんの4分の1、具体的には前立腺ガンの 42%、腎ガンの 42%、甲状腺ガンの 73%、悪性黒色腫の 58%が過剰診断されており、女性でも甲状腺ガンの 73%、悪性黒色腫の 54%、乳ガンの 22%が過剰診断であったということです。同様の研究はアメリカでも行われており、過去40年間のデータを精査したところ、甲状腺ガン、腎臓ガン、および悪性黒色腫の発生率が急激に上昇している一方で、ガンによる死亡数はほとんど変化していないことが判明したということです。
近年、がんに対する検査精度が向上していることや、がん検診の普及などでがんが発見されることが多くなっていますが、検診などで発見される1cm程度以下のがんに関して、京都府立医科大学名誉教授の渡辺泱(ひろき)博士によると、がんがどんどん大きくなって生命を脅かすものは全体の2割程度にすぎず、残りの80%についてはがんの成長が遅かったり、あるいは自然と増殖が止まってしまうそうです。ただし全体の5%程度は急速に大きくなるような悪性度の高いものだそうです。このような見方は現在では多くの研究者の間で共通認識となっており、欧米では悪性度が高くないがんの可能性が高いケースでは、がんが見つかってもすぐに抗がん剤や放射線療法などを行わず、まずは意図的監視(経過観察)を続けるというのが主流となっています。同博士によると、がんが見つかればすぐに手術や化学療法を行うことは患者にとってマイナスが大きいとしながらも、がん検診などで発見される悪性度の高いがんに関しては早期に治療するべきであり、がん検診などを否定するものではないとのことです(※)。
発がんのメカニズム
がんは細菌やウイルス、あるいはある種の化学物質によって細胞の遺伝子が傷つけられることによってがん化して、その後も次々と変異して大きくなるという説(多段階発がん説)が定説となっていますが、実はそのメカニズムについてはよくわかっていません。
渡辺泱(ひろき)博士によると、京都大学ips細胞研究所の山田泰弘教授らの実験でips細胞作製の技術を使って腎の正常な体細胞を中途半端に初期化すると腎がん細胞になり、さらに同じ技術で初期化を進めると多能性幹細胞まで戻ったという論文を紹介しつつ、あくまで個人的な見解として、体細胞の中途半端な初期化の過程こそが発がんの原因ではないかとのことです(ips細胞=人工多能性幹細胞で、体細胞へ数種類の遺伝子を注入することで多能性幹細胞にしたもの)(※)。受精卵から多能性幹細胞が生まれ、更に臓器幹細胞となって、内臓をはじめ肉体が形成される過程について、中国哲学的に考えると、「生の来るはこれを精という」(黄帝内経)、「両神あい搏(う)ち、合して形をなす、常に身に先じて生ずるは、これを精という」(同)とあり、多能性幹細胞は“精”という概念で捉えられています。よって、“精”が充実していることは肉体が健康でいるためには欠かせない要件といえます。また、「神を失する者は死し、神を得る者は生くるなり」(同)とされ、生命は一生を通じて“神”の制御を受けていることになっています。特にがんに関しては前漢の時代の淮南子(えなんじ)に「神は形より貴なり。故に神(形を)制すれば則ち形従ひ、形(神に)勝れば則ち神窮す」とあり、五臓の“心”を通じて“神”とのつながりを保つこと、すなわち精神を健全な状態に保つことが、がんにならないだけでなく肉体の健康状態を維持するのには重要であると考えられています。ストレスなどにより“心”が“神”とつながりにくくなると“精”(=幹細胞)から体細胞への変化が逆行して体細胞ががん化するとも考えられますし、がんができても“神”とのつながりを回復するとがんの成長も止まる可能性があるのではないかとも思います。
(※参考文献:渡辺泱著「検診で見つかるがんの8割は良性がんである」)